- 2025.09.01
-
- 不動産登記
- 相続
- 相続コラム
就籍届による戸籍と相続登記について
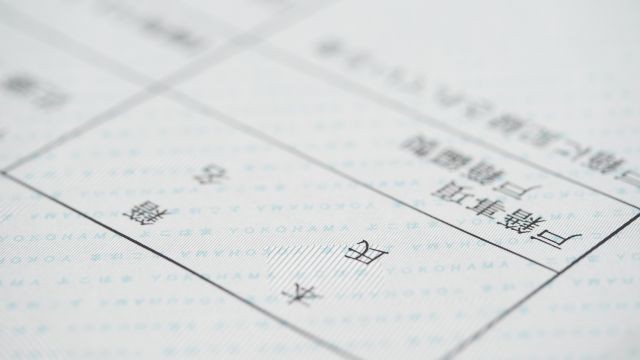
はじめに
相続登記には、原則として被相続人の出生から死亡までの戸籍が必要になります。被相続人の死亡の戸籍から出生時までさかのぼることにより、相続人を確定します。しかし、被相続人の戸籍の一部について取得できない場合があります。
相続登記に必要な戸籍(除籍・原戸籍)が添付できないときの扱い
上記のようなケースとしては、例えば、戸籍謄本が役所の火事、戦争、震災、津波等でなくなってしまった場合があります。特に戦争時、関東大震災時に戸籍が焼失してしまったケースはかなり多くあります。
このような場面、以前の取り扱いは「戸籍(除籍・原戸籍)が発行できません」という市区町村長の証明書と「他に相続人はいません」という相続人の署名捺印入りの上申書(印鑑証明書付き)を作成、提出することで法務局に相続登記を進めてもらっていました。しかし、この相続人の署名捺印入りの上申書を用意することが難しいケースが増えたことから、平成28年に「戸籍(除籍・原戸籍)が発行できません」という市区町村長の証明書があれば「他に相続人はいません」という上申書は不要であるという通達が出ました(平成28年3月11日付法務省民二第219号法務省民事局長通達)。
参考:https://www.moj.go.jp/content/001378575.pdf
現在は、このように戸籍謄本の発行の請求をすることはできない場合は、「滅失証明書」「焼失証明書」「告知書」等の証明書を役所に発行してもらうことで対応していきます。
就籍届による戸籍
先日相続登記のご依頼をいただいた際、上記以外の理由により被相続人の戸籍が(死亡から)24歳時点のものまでしか取得できないケースがありました。私が初めて見た戸籍でしたのでご紹介したいと思います。この被相続人の方は、何らかの理由により24歳まで無戸籍で、24歳の時点で就籍の届がなされていました。「就籍」は、戸籍がつくられる原因の一つです。通常の日本国籍者であれば本籍があり、当然戸籍がありますが、無戸籍という方もいらっしゃいます。このように日本国籍を有しているにかかわらず無戸籍の方が、家庭裁判所で就籍の許可審判を受けることで、あらたに戸籍がつくられることがあります。
就籍により従前戸籍がない場合における上申書の要否について
就籍届による24歳までの戸籍しかない場合(つまりもともとあった戸籍が焼失や滅失したのではなく、そもそも戸籍が無い場合)、相続登記を申請するにあたって、「他に相続人はいません」という上申書は必要なのでしょうか。
これについて、申請前に管轄である青森地方法務局に書面で照会をしましたが、法務局の回答は、平成28年3月11日付法務省民二第219号法務省民事局長通達どおりと考え、就籍届までの戸籍の添付で相続登記に差支えありません(上申書は不要)、とのことでした。
なお、これはあくまで青森地方法務局での話であって、他の法務局での取り扱いも同じであるとは限らず、また登記官により見解が異なる可能性もございますので、案件ごとに照会されるのをおすすめいたします。
おわりに
様々な事情により被相続人の戸籍の一部が取得できないケースがあることがお分かりいただけましたでしょうか。一方で、不動産に限らず、法定相続や遺産分割による相続手続きでは、一般的に被相続人の死亡から出生までの戸籍が必要となりますが、相続財産に関する有効な遺言書がある場合は、被相続人の戸籍について出生まで遡る必要がなく、死亡の記載のある戸籍謄本だけで手続きをすることが可能ですので、生前に遺言書を作成しておくという対策を取ることも可能です。戸籍が取得できない場合の相続登記についてお困りの場合や、遺言書作成のご相談は是非神楽坂法務合同事務所へご相談ください。
(文責:村上)