- 2025.07.14
-
- 相続
- 相続コラム
株式の相続について
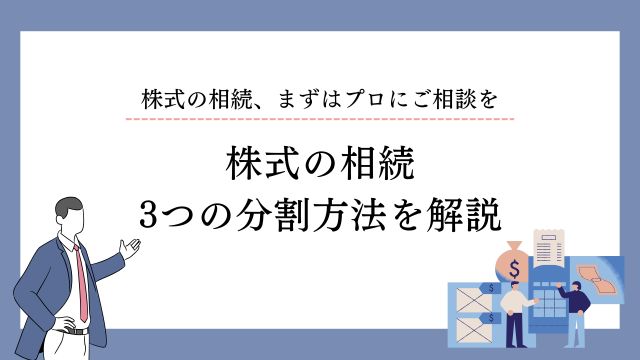
はじめに
弊所で受任する遺産承継業務のひとつに株式の相続手続きがあります。相続人が複数名存在する場合、被相続人の株式は相続によって各相続人の法定相続分に応じて当然に分割されるというわけではなく、遺産分割がなされるまでの間は、相続人の準共有状態になると解されています。
例えば、被相続人名義のA株式会社の株式が100株あり、相続人が配偶者、長男、二男の3名である場合、A株式会社の株式100株は、配偶者、長男、二男3名の準共有状態にあるということになります。配偶者が法定相続分である50株(2分の1)、長男と二男がそれぞれ法定相続分である25株(4分の1ずつ)について、当然に株主となるわけではありません。
株式の権利の中には株主総会での議決権など、分割が困難な不可分な権利が含まれています。そのため、預貯金等と異なり単純にこれを分割して各相続人に帰属させることができません。よって、株式は相続と同時に法定相続分で分割されないため、相続財産に株式がある場合は遺産分割をする必要があります(参考:最判平成26年2月25日)。
遺産分割協議
株式の遺産分割方法には以下の3種類があります。
現物分割
株式を換金せずに株式のまま受け継ぐ分割方法です。例えば、株式全部を1人の相続人が相続する場合も現物分割です。また、2種類の銘柄を相続人2人で分ける方法も現物分割となります。株式は不動産と違い、数で平等に分けることができるため、現物分割が一般的な分割方法です。
代償分割
株式を1人の相続人が相続し、他の相続人に代償金を支払う分割方法です。例えば、兄弟2人の相続で兄が評価額1,000万円相当の株式を相続し、弟に現金500万円を支払うといった方法です。この場合、兄弟それぞれ相続により取得する財産は500万円ずつとなります。
換価分割
株式を売却して売却代金を相続人間で分ける分割方法です。売却代金は、法定相続分に従って分配することも、遺産分割協議で別の分け方をすることも可能です。相続人全員が株式に関心がなく、現金で取得したいといった場合などは、換価分割が適しています。
遺産分割協議がまとまったら、株式を相続することになった相続人が会社に対し名義変更等の手続をとり、株主としての権利を行使することになります。
株式を相続することとなった相続人が被相続人と同じ証券会社の口座を有している場合は、相続した株式を被相続人口座から相続人口座に移動するのみで手続きは終了ですが、相続人が被相続人と同じ証券会社の口座を有していない場合は、相続人は新しく証券会社に口座を作った上で、被相続人の株式を被相続人口座から相続人口座に移動する必要があります。
証券会社が不明の場合
被相続人が株式を持っていたが、どこの証券会社に預けているのか不明といった場合には、証券保管振替機構に対して開示請求をすることで、被相続人が預託している証券会社を判明させることができます。ただし、被相続人保有銘柄まで直接調査することができませんので、証券会社に対して別途手続き(残高証明書の申請など)を行う必要があります。
おわりに
被相続人名義の株式を相続人がスムーズに相続するためには、被相続人が生前に家族に対して証券口座や保有銘柄等の情報をきちんと伝えておくことが大切です。
株式の相続手続きには不動産や預貯金の手続きと同様、戸籍や遺産分割協議書等の必要書類を要します。弊所では不動産の相続登記や預貯金の解約、株式の相続手続きをパーッケージとした遺産承継業務もお受けいたしますので、複数種類の財産に関する相続手続きは是非まとめて神楽坂法務合同事務所へお任せください。
(文責:村上)