- 2025.08.01
-
- 相続
- 相続コラム
株式の未受領配当金の相続について
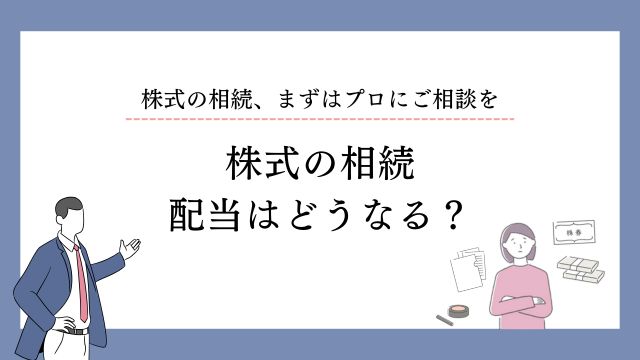
はじめに
株式を発行した企業は、一般的に、利益を上げると株主にその一部または全部を分配します。その分配された利益のことを「配当金」といいます。株主は、株式を保有し続けることで、保有株数に応じて配当金を受け取ることができます。したがって被相続人が株式を保有していた場合は配当金を受けていた可能性がありますが、配当金の受け取り方次第では、相続の開始により配当金が未受領になってしまうことがあり、その場合は株式の相続手続きと合わせて未受領配当金の手続きも必要になります。
証券会社は被相続人の株式を管理していますが、株式の配当金の管理は、株主名簿管理人となる信託銀行が行っています。証券会社は相続により名義変更がなされると速やかに株主名簿管理人に通知しますが、原則として、証券会社で配当金の管理はしていないため、名義が変わったからといって自動的に、配当金も新名義人の口座に入るということにはなりません(※ただし、被相続人が「株式数比例配分方式」を選択していた場合、配当金はすべて証券口座で受け取っていますので、未受領配当金が生じることはありません)。
相続が発生してすぐに名義変更ができるケースは少なく、相続が発生してから被相続人名義の口座から相続人名義の口座に移管されるまで、一定の時間が経過するケースがほとんどですので、その間に発生した配当金は、どなたにも支払われないままとなってしまいます。
配当金の受け取り方法
未受領配当金について、ご説明するにあたり、そもそも配当金の受取方法にはどういったものがあるかということですが、大きく分けて3つあります。
1.株式数比例配分方式
証券口座で受け取る方法です。
被相続人がこの方式を選択していた場合、未受領配当金は発生しません。1銘柄でも特別口座(信託銀行で管理している株式)があるとこの方式は選択できません。
※特別口座とは
特別口座とは、株券電子化(2009年1月5日実施)の前に証券会社を通じて「証券保管振替機構(ほふり)」に株券を預託されなかった(いわゆるタンス株等の)株主の権利を保護するために、発行会社により信託銀行等に開設された口座のことです。
2.登録配当金受領口座方式、個別銘柄指定方式
登録配当金受領口座方式(一括振込方式)は保有する全ての上場株式の配当金を一つの銀行口座で受け取る方法です。個別銘柄指定方式は、銘柄ごとに銀行口座をわけて受け取る方法です。
3.配当金領収証方式
株主宛に「配当金領収証」が送付され、指定期間内にゆうちょ銀行等の窓口に持って行き配当金を現金で受け取る方法です。
被相続人が、上記1.ので配当金を受け取っていた場合、未受領となっている配当金はありません。証券口座の相続手続きのみで完了となります。
上記2.の方式で配当金を受け取っていた場合、指定していた銀行口座が凍結された時点で配当金を受け取れなくなるため、未受領配当金が生じます。そのため、配当金を管理する株主名簿管理人(信託銀行)に連絡をして、相続手続きを行い、配当金を受領します。
上記3.の方式で配当金を受け取っていた場合ですが、配当金領収証には、銘柄ごとに窓口での払渡期間が設定されています(到着後1か月以内であることがほとんど)。払渡期間内の場合は、配当金領収書と相続関係書類を準備してゆうちょ銀行の窓口へ持参して手続きを行います(一部ゆうちょ銀行以外の企業あり)。配当金の額によっても手続き方法(窓口or郵送、必要な書類等)が異なりますので事前に金融機関へ確認されることをおすすめします。
払渡期間を過ぎた場合でも配当金の受取は可能ですが、株主名簿管理人(配当金領収証記載の信託銀行)に連絡をして別途手続きが必要となります。また、配当金領収書を紛失していた場合は、株主名簿管理人(信託銀行)へ連絡して発行を依頼します。
未受領配当金があるかどうか不明な場合
上場株式の株主名簿管理人へ未払配当金残高証明書の発行を依頼します。インターネットで「〇〇株式会社 株主名簿管理人」と検索するとその企業の株主名簿管理人となっている信託銀行が確認できます。依頼書は信託銀行によって異なりますが、「証明書等発行依頼書」「証明書交付請求書」などと呼ばれます。この依頼書は、信託銀行の証券代行部に電話をして請求するか、信託銀行によってはホームページからの入手も可能です。
おわりに
多くの企業では、未受領配当金の受取期間が3年から5年に設定されており、受取期間を経過すると配当金を受け取る権利が失われます。この期間は「除斥期間」と呼ばれ、企業の定款に基づいて決まっています。なお、民法上の債権消滅時効は10年ですが、企業は事務的負担を軽減するために、独自に短い期限を設定することが一般的です。未受領配当金があることが判明した場合は受取期間を確認し、期間内であれば早めにお手続きされることをおすすめします。
(文責:村上)